
「夏の暑い日に、ひんやりした金属のボールに
スライスした氷を盛り付けて、シロップをかけて
食べる…これって、品があるわよねぇ」
えっ、「それってただのかき氷でしょ」って?
そう、現代なら当たり前のシーンかもしれませんが、
それが1,000年も前の話だとすると?
元の文章は…
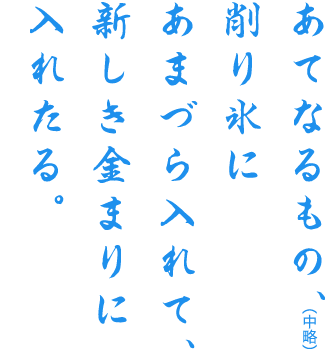
これを書いたのは平安時代に枕草子(まくらのそうし)を書いた女流作家、あの清少納言(せいしょうなごん)です。「あてなるもの」とは「上品なもの」ということ。彼女が生きた平安時代に冷凍庫はもちろんありませんでした。「氷室(ひむろ)」という貯蔵庫に氷を保存していたのですが、当時の氷は実に貴重なもの。それをおやつにするなんてずいぶんぜいたくなことだったのです!ついついエッセイ(枕草子)にも残したくなるワケですね。
御簾(みす)
御簾とは、あんだ竹ひごのフチを布で囲んだスダレのこと。日よけだけでなく、目かくし、仕切りなどにも使われていました。
寝殿(しんでん)
づくり
貴族が住むのは寝殿づくりと呼ばれるつくりの家。カベが少なく几帳(きちょう)というもので部屋を仕切っていただけ。風の通りが良く夏も快適でした。
扇(おうぎ)
平安時代は夏になると着物だけでなく扇も衣がえ。ヒノキから涼しげな竹と和紙を使った夏用へ変えていました。
参考文献:「氷の文化史」(田口哲也著、株式会社冷凍食品新聞社、1994)